社員がイキイキと活躍し、会社が持続的に成長・発展する「好循環経営」のススメ
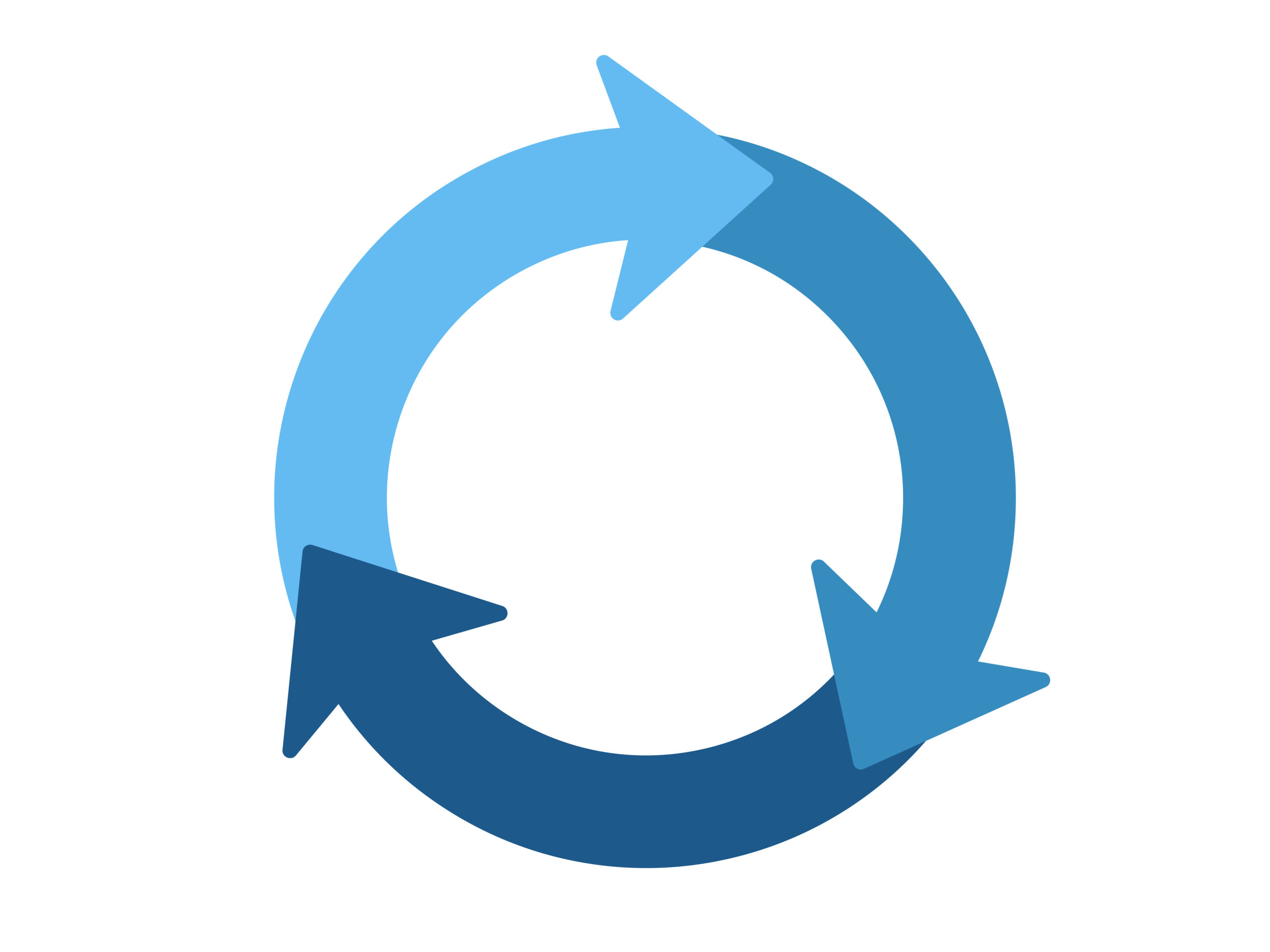
目次
はじめに:経営の究極の目的
「あなたが会社を経営する、事業を行う究極の目的はなんですか?」と聞かれたら、経営者の皆さんだったらなんと答えるでしょうか。
「売上や利益を拡大して、会社を持続的に大きくしていきたい」あるいは「業界で一目置かれる存在になりたい」など、いろいろな答えがあると思います。
それはとても重要なことですよね。
私も経営者の端くれですが、もちろん売上や利益を高めて、今やっている事業を拡大していきたい、人材育成や組織づくりのお手伝いをする上でのブランド価値を高めたいという気持ちはとても強くあります。
みんな生きていかなくてはいけませんし、経営者であれば社員に給料を払って、家族もろとも生活できるようにしてあげないといけません。
つねにそのことで頭が一杯かもしれませんね。
でも、売上や利益を上げることやブランド価値を上げることなどは、事業を続けていくために必要なことですが、一つの要件であって「究極」の目的ではないのではないかと思います。
自分の会社が売上や利益を拡大し、ブランド価値を高めることによって、どんな理想的な状態を生み出したいのか、どんな社会や世界を実現したいのかということが、究極の目的になるのではないでしょうか。
この目指す理想的な状態というのは、それぞれの経営者、会社によって違うと思いますが、やはりお客様の役に立つ、お客様に心から喜んでもらえるこんな価値(製品やサービス)を提供したい、自分たちが事業をすることによって世の中の人びとや社会にこんな良い影響を与えたい、世界をこんな状態にしたいなど、最終的には人の、あるいは人々の本当の満足や幸福につながるような理想的な姿ではないかと思います。
志のある経営者の皆さんには、なんらかの心から実現した理想的な状態、ビジョンがあるはずです。
そして、その実現したい理想的な状態やビジョンが大きければ大きいほど、経営者だけでは実現することができず、社員の協力が不可欠です。
それも、ただ経営者の言うことを聞くだけではなく、自ら考え、行動し、社員同士で協力し合う、主体的な社員が必要です。
ですから、理想を実現したい経営者にとっての最大の課題は、「どうしたら社員はもっと主体的に働いてくれるようになるのか」「社員がより主体的に働く自律型組織は具体的にどんな経営をしたら実現できるのか」ということに集約されるのではないかと思います。
社員の主体性を高めるにはどうしたらいいのか
社員が主体的に働くというのは、さきほども出てきましたが、社員が自ら考え、行動し、仲間と協力し合う働き方ができるようになるということです。
したがってテーマは、「どうしたら社員は自ら考え、行動し、仲間と協力し合うようになるのか」ということです。
とても難易度の高いテーマですが、経営をするにあたって昔からある最大のテーマの1つと言ってもいいと思います。
自ら積極的に判断したり、行動したりする主体性というのは、人の内側から湧き上がってくるもので、本人以外の人間が直接コントロールしたり、強制したりすることはまずできません。
私の娘は中学・高校となかなか勉強しなくて、脅したり、すかしたり、おだてたり、ご褒美をちらつかせたりしましたが、一切効果はありませんでした。
そうすることによってますます勉強に嫌気がさし、嫌いになっていったのではないかと思います。
外側から圧力をかけることによって、ますますやる気という主体性を私自身がつぶしていたんだと思います。
外側からの力(外発的動機付け)では家族すら主体的になるようにコントロールすることができないのですから、ましてや社員を外側のコントロールで本当の意味で主体的にすることはできないでしょう。
では、どうしたらいいのか。
社員に主体性を発揮してもらうため経営者ができることは、社員が自然に主体的になるようなきっかけや環境をよくよく考えて整え、社員が主体的に考え、行動し、協力し合うようになるのを待つしかないと思います。
そして、社員が自然に主体的になるようなきっかけや環境を整える上で重要なことは、社員が仕事をとおして自ら幸福度を高められるような経営をしていくことです。
人は、不安であったり、幸福感を感じられないような場所では、当然積極的・主体的になることはできません。
したがって、社員に主体的に働いてもらうためには、社員が仕事を通じて自ら幸福度を高められるような仕組みをまず整えることが重要なのです。
社員の幸福度が高まると、社内に好循環が生まれる
それでは、社員の幸福度や主体性が高まると業績にどんな影響があるのか、少しデータを見てみましょう。
皆さんも耳にしたことがあるかもしれませんが、イリノイ大学の研究によると、幸福度の高い社員は、そうでない社員に比べて、創造性は3倍、生産性は平均で31%高く、売上は37%高いとのデータがあります。
また、ギャラップ社の調査では、主体性(エンゲージメント)の高いチームは低いチーム比べて、収益性は22%、生産性は21%、株価収益率は47%それぞれ高く、離職率は大幅に低下し、品質の欠陥は41%、事故は50%低いといっています。
これらの調査では、社員の幸福度やチームの主体性が高まることで、創造性や生産性などのプラス要因が高まるだけでなく、トラブルや事故などのマイナス要因が低下することも示しています。
この構造をもう少し細かく分解して、そのメカニズムをみてみましょう。
「社員の幸福度が高まる → 社員の主体性(エンゲージメント)が高まる → 社員同士のコミュニケーションが深まり、信頼や心理的安全性の高い組織が生まれる → 組織の創造性や生産性が高まり、ミスやトラブルが減る → お客様や社会の人びとにより優れた価値を提供できるようになる → 多くの人びとに喜んでいただけるようになる → 売上・利益が高まる → 報酬や福利厚生を充実できる → 社員のやりがい・誇り・自信が高まる → 社員の幸福度がさらに高まる」という好循環が生まれると思います。
そして、この好循環を生み出す起点が、社員の幸福度が高まることです。
先ほど、社員が自ら幸福度を高めることができるような仕組みを整えることが重要だとお伝えしました。
それでは社員は何が満たされたら幸福度を高めるのでしょうか?
次に人間が幸福を感じるために求めている「本質的な4つの欲求」について見ていきましょう。
社員が本当に求めている「本質的な4つの欲求」
社員の幸福度を高めるためには、社員が良い人生、充実した人生を送るために求めていることを仕事や会社をとおして満たせるようにすることが重要です。
社員は人生を良いものに、充実したものにするために、どんなことを求め、重視しているのでしょうか。
弊社が企業の人材育成や組織づくりのお手伝いをするときには、最初にクライアント企業の各層の社員5~10名に対して、いわいる会社や仕事に対するエンゲージメントの状態を把握するための定性的なインタビューを行います。
企業理念に対する共感や普段どんなことを心がけて仕事をしているかなど40数問ある質問の最後にする質問が、「あなたの人生を充実した、楽しいものにするために、もっとも必要なもの、重要なものは何ですか?」という質問です。
社員の皆さんが人生でもっとも大切にしていること、重視していることを聞いているわけですね。
いろいろな企業でこの質問をしていますが、ほぼ4つに集約されます。
これは他の記事でも何度もお伝えしているのでご存じの方もいると思いますが、
- やりがい
- 良い人間関係
- お金(安全・快適)
- 成長
の4つです。
中でも、やりがいと良い人間関係をとても強く求めています。
そして、お金(安全・快適)、成長は、やりがいと良い人間関係を得るために必要なものと考えているようです。
あなたの会社では、社員のやりがいの度合いはどうでしょうか、そしてどのくらい良い人間関係をつくることができているでしょうか。
さらに、ここが重要なのですが、社員が幸福度をたかめ、その結果として主体性(エンゲージメント)を高めていくためには、経営者や上司が社員を人としてその存在を認め、尊重する、大切にするというということがその前提としてとても重要なります。
社員は、どんなに仕事にやりがいを感じ、職場で良い人間関係を結べていたとしても、経営者や上司が自分という存在を認めていなかったり、信頼していなかったりしたら、幸福感は感じるかもしれませんが、会社に対する積極的な・主体的な気持ち、いわゆるエンゲージメントは高まらないでしょう。
社員の主体性が高まらなければ、組織の創造性や生産性も高まらないので、お客様や社会の人びとになかなか喜んでもらえず、業績も振るわないという状況になってしまいます。
ですから、社員の幸福度を高め、主体性の高い状態を生み出す大前提として、社員一人ひとりの可能性を信じ、尊重することがまず必要になります。
社員の主体性が高まり、会社が持続的に成長・発展していく「好循環経営」の実現方法
社員の主体性が高まることによって優れた価値を提供し続けることができるようになり、会社が持続的に成長・発展していくようになれば、社員にとっても、経営者にとっても、お客様や社会にとってもとてもハッピーな状態が生まれます。
この状態を生み出すためには、社員の幸福度を高めるために社員の本質的な4つの欲求=やりがい、良い人間関係、成長、安心・快適(お金を)を満たすこととお客様や世の中に優れた価値を提供し続けるという2つのことを同時に実現する経営が求められます。
この経営を実現するには、下記の5つのステップを踏む一貫性のある組織づくりが必要です。
- 人を中心におく企業理念を言語化する
- 優れた価値を提供するための経営方針・目標の明確化(やりがい・誇り)
- 信頼・心理的安全性を高める組織文化づくり(良い人間関係)
- メンバーの良い試行錯誤を促すマネジメント(成長)
- 労働条件・職場環境・福利厚生の充実(安心・快適(お金))
この5つのステップを踏む組織づくりを段階的に進めていけば、社員の幸福度と主体性を高めながら、お客様や世の中に優れた価値を提供し続けるという2つのことを同時に実現でき、社内に好循環を生みだすことができるようになります。
もちろんこの5つのステップ全部に取り組むことができれば本当に理想的な会社になることができると思いますが、全部をやる必要はないと思います。
会社の状況は千差万別ですので、その会社の現状に合わせて、5つのステップのうち2~3つを組み合わせて取り組めば、一般的な会社を凌駕する好循環を社内に生み出すことができると思います。
それぞれのステップを簡単に見ていきましょう。
ステップ1:人を中心におく企業理念の言語化
まず、人々の役に立ったり、社員を含めた人々の幸福に貢献することを謳う企業理念を明確にすることが必要です。
この人中心の企業理念がなければ、次のステップの「優れた価値を提供するための経営方針・目標の明確化」をすることができません。
人は、人々の役に立つ、喜んでもらう、その幸福の後押しをすることにやりがいや誇りを感じるわけですから、そうしたやりがいや誇りを感じる経営方針や目標を設定するためにも、人中心の企業理念がまず必要になります。
もちろん、もうすでに人を中心におく企業理念を持っている企業も多いと思いますので、その場合はこのステップをスキップして、現在ある企業理念にもとづいて次のステップ2に取り組んでいけばよいと思います。
ステップ2:優れた価値を提供するための経営方針・目標の明確化(やりがい・誇り)
人を中心におく企業理念にもとづいて、お客様や世の中に対して優れた価値を提供するための道筋を明確にします。
まず、わが社は「こんな価値を提供できる、こんな会社になりたい」というありたい会社の理想の姿である、3~5年後ぐらいを見据えた中期ビジョンを設定します。
そしてこの中期ビジョンは、社員全員がワクワクできるような現実的でありながら夢のある「こんなことが実現できたらいいよね」という内容にしたいので、経営幹部や一般社員をメンバーとする5~8名ぐらいのプロジェクトチームで策定するのが望ましいと思います。
そして、ワクワクする中期ビジョンが描けたら、そのビジョンを実現するための経営戦略を立案します。
さらに、経営戦略を踏まえて、今年度は全社、各部署、各人で何を目指すのか、具体的な目標を設定し、その進捗状況を定期的に確認しながら進んでいきます(OKRの導入・運用)。
このことによって、社員の目標が達成できると自分が所属する部署の目標が達成でき、各部署や全社の目標が達成できれば、経営戦略や中期ビジョンが実現し、経営戦略や中期ビジョンが達成できれば、人中心の企業理念の実現に近づくという道筋が分かるようになるので、社員は今自分が取り組んでいる仕事にやりがいや働く意味、誇りを感じられるようになり、幸福度や主体性が高まります。
ステップ3:信頼・心理的安全性の高い組織文化づくり
どんなにやりがいを感じるビジョンや目標があったとしても、人は安心できる良い人間関係の中にいないと主体的にのびのびと仕事をすることはできません。
ですから、このステップ3はステップ1の人中心の企業理念の言語化の次に重要なステップになります。
そして、信頼・心理的安全性の高い組織文化をつくるためには、経営者や幹部の皆さんの人に対する価値観や社員との真摯な向き合い方が非常に大きな影響を及ぼします。
まず、社員一人ひとりには必ず良いところや可能性、純粋な想いがあることを無条件に信じ、人として尊重するという文化をつくる必要があります。
でもこれは結構簡単にはできないんですよね。
これさえできれば、実は社内に好循環が生まれてしまうというぐらいインパクトの大きいことなのですが、経営者の方や幹部の方は、なかなか社員を無条件に信じ、人として尊重するということができないケースが多いのです。
それはなぜかというと、経営者や幹部の皆さんはビジネスを前に進め、業績を上げることに意識を集中していて、自分自身の中にある良いところや可能性、純粋な想いに意識を向けることを忘れがちだからです。
ですから、経営者や幹部の皆さん自身が自分の中に良いところや可能性、純粋な想いがあることを想い出し、信じることができるようになれば、自然と社員の良いところや可能性、純粋な想いを無条件に信じ、尊重することができるようになります。
弊社は、この経営者や幹部の皆さんが自身の中にある良いところ、可能性、純粋な想いを再発見し、そこに意識を向けていく状態になることをとても重視しています。
これさえできれば、あとは人とのちょっとした向き合い方のコツを学べば、信頼を結んだり、心理的安全性の高い組織文化をつくることはそんなに難しいことではないと思います。
ステップ4:メンバーの良い試行錯誤を促すマネジメント(成長)
このステップ4からは、社員が主体性を高め、優れた価値を提供できるようになる「好循環経営」を実現する上では応用編になります。
ステップ1からステップ3は「好循環経営」を実現するための基礎編で、このステップ1から3をある程度実現できればかなりの好循環が社内に生まれることになりますが、さらに好循環のレベルを上げていきたいと思ったら、また余裕が出てきたら、ステップ4,5に進んでいくとよいと思います。
メンバーの良い試行錯誤を促すマネジメント(成長)ですが、これは管理職の皆さんが社員の皆さんの主体的な成長を後押しするための取り組みです。
人は、すべて言われたことを言われたとおりにやっていても、ほとんど成長しません。
やはり、仕事のある程度の部分を任され、自分でやり方などを考えて、行動してみて、その結果を振り返り、今度はこうしたらいいんじゃないかと試行錯誤をしないと人は成長しないでしょう。
ですから、管理職の皆さんは社員を信じて、仕事を任せ、良い試行錯誤を促すことが重要です。
でも、言葉は悪いですが、ただ丸投げで社員に仕事を任せればいいということではありません。
重要なことは、社員がスムーズに、迷いなく試行錯誤ができるように、適切なケアをすることです。
ポイントの一つは、社員に仕事を任せる場合、その仕事の目的とゴールのイメージは上司と部下の間で握っておき、その目的とゴールを達成する方法ややり方は部下に全面的に任せるということです。
そして、なるべく部下が自律的な判断ができるように、可能なかぎりの情報(経営情報も含む)を提供してあげることです。
そして、任せっぱなしではダメで、目的やゴールを達成するやり方を全面的に任せた上で見守ってあげる必要がありますし、時々仕事の進捗状況を確認する場を設け、フィードバックをしたり、手助けが必要であれば部下の主体性を損なわない程度の手助けをしてあげます。
そして、部下が自力で成果を上げたら、自分のことのように一緒に喜んだり、感謝したりすることです。
こんなマネジメントができると、社員は自分の成長を実感することができるようになると思います。
ステップ5:労働条件・職場環境・福利厚生の充実(安心・快適(お金))
1~4あるいは1~3のステップである程度組織が順調に回り始めると、社内に好循環が生まれます。
そして、社内に好循環が生まれると、会社全体の売上や利益が高まり、余裕が出てきます。
そうしたらステップ5の報酬水準のアップや働く環境・福利厚生を充実していけばいいと思います。
そうすれば、社員の幸福度や主体性をさらに高めることができるでしょう。
特に報酬については、社員の皆さんが同業他社よりも優れた価値を提供してくれた結果として売上や利益が上がったことになるはずですから、それに見合う形で業界の報酬の平均的な水準の1~3割増しの比較的高い報酬を払うことを目指すとよいと思います。
高い水準の給料を払えるのは経営者の優れた経営の証と思っていただいてよく、誇っていただければと思います。
安全対策や健康対策、DX、おしゃれなオフィスなど安心・快適・効率的に働ける職場環境づくりも、利益率などを見ながらできる範囲で充実していけばいいと思います。
このステップはどちらかというと社員にとっては衛生要因なので、不足していると不満につながりますが、充実すれば充実するほど社員の幸福度や主体性があがるかというとそういう性質のものではないので、できるだけ充実するというスタンスで、経営者が社員にしてあげたいと思うことをやってあげればよいと思います。
まとめ
お客様や世の中の人びとに優れた価値を提供し、会社が持続的に成長・発展していく好循環を社内に生み出してく起点は、社員が自ら考え、行動し、協力し合う主体的な働き方できるようになることです。
そして、社員の主体性が高まる土台となるのが、社員の幸福度を高めることです。
社員の幸福度を高めるためには、人間が幸せになるために本当に求めている「本質的な4つの欲求」を満たしながら、同時に優れた価値の提供を追求する経営を実現することです。
社員の幸福度が高く、優れた価値の提供を追求する会社は社員にとって魅力的な会社であり、その会社で働けることは幸せです。
そして、優れた価値の提供を追求し続ける経営ができれば、お客様や世の中の人びとの役に立ち、喜んでもらえるようになるので、売上や利益が高まり、社員もやりがいや誇り、自信をさらに高めてイキイキと働くようになるので経営者もハッピーになります。
この一貫性のある組織づくりである「好循環経営」は、社員も、経営者も、お客様も、世の中の人びとも幸せにする経営です。
そしてこの「好循環経営」を多くの企業が志向したら、多くの人が幸福感を味わうことができるすばらしい世界が生まれると思います。
ぜひ一緒に目指しませんか?
当社では、それぞれの企業の人材や組織に関わる課題解決の方向性を整理する個別相談を行っています。
こんな課題があるんだけど、何から手をつけたらよいかわからないというような場合は、一緒に課題を整理して最重要課題を見つけ、どのような解決策をどんな順番で取り組んだらよいかを見出すサービスです。
お気軽にお問い合わせください。
↓









